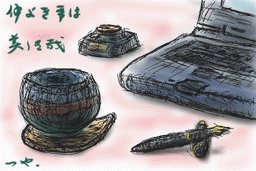
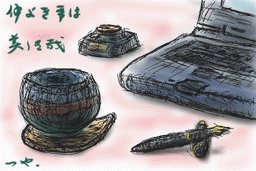
エッセー(2002.11.9追加)
エッセー(2000.4.13追加)
今年の始めから、MacFan letterというメールマガジンで、週に1回、コラムを書いている。まあ、せいぜい原稿用紙にして2枚とちょっとの小さなコラムなんだけど、これがなかなか大変なのだ。
どうも僕はコラムだのエッセーだのといったものが苦手だ。こういうものになると「普通 の意見を書いてはいけない」と思ってしまうので、なんとか毛色の変わった見方、考え方を提示しないといけないと四苦八苦してしまうのだ。MacFan letterの短いコラムにしたところで、実は書くのに4〜5時間はかかっている。4時間もあれば、テクニカルな原稿ならその10倍は書けるだろう。実にコストパフォーマンスの悪い仕事だ。
それ以上に困るのは、コラムやエッセーに書いていることを「これは掌田が心底信じていることなのだ」と勘違いされてしまうことだ。――僕は、エッセーやコラムというのは「新しい見方を提示する仕事」だと思っている。普段、「こうだ」と決まった見方しかしていないところに、「こういう見方もあるんじゃない?」ということを見せる仕事だ。
だから、自分ではたいして信じてないことを「きっとこうだと僕は思う」と平気で書いたりすることもある。これは、別 に嘘を書いているわけじゃない。どう書けば面白いかいろいろ考えた結果なのだね。その結果 、書き始めた時とは正反対の立場に帰着することもある。例えば、「バナー広告はダメだ」というコラムを書き始めたとしても、途中であれこれいじって「この方が面 白い」となれば、「これからはバナー広告だ!」としてしまうこともある。要は、「どっちのほうが読んで面 白いか」だ。面白ければ、自分がどう思ってようが関係なく、そちらにする。それがサービス業というものだ。
また、書き方も「その方が面白い」と思えばそちらを採用する。例えば、カッカと熱くなって思わず書いてしまいました、という感じの文章にしたほうが面 白い!となれば、そういう文体で書く。どうやら僕は「熱くなって原稿を書く人」と思われることがあるようだ。そんなことなどあり得ないのに、それが多くの読者にはわからないらしい。冗談ではない。これでももの書きの端くれである。まかりなりにも文章を書くプロなのだ。「冷静に書いた文章」と「興奮して書いた文章」ぐらい書き分けられずに原稿料で飯が食えるものか。(←例えば、これが「熱くなって書いた文章」ね)
更に、こういう世界では「会社の悪口はいってもいいが、読者の悪口はいってはいけない」という不問律がある。どんなにそれが正しいと思っても、「ユーザーはバカだ」とは絶対書いてはいけない。だけど、僕はそのほうが面白ければ「ユーザーはバカだ」と書いてしまう。ウケればこっちのもんなのだ。毒にも薬にもならないより、「あの掌田ってバカは許せない!」といわれたほうが遥かに読者も増える。僕を攻撃する人は、間接的に僕の営業活動を手伝ってくれてることに気づかないみたい。ほんと皆さん、お世話様です(笑)。
パソコンの世界では、不思議なものでエッセーやコラムのことを「小論文」か何かのように勘違いしている人が多い。僕のように「これは読み物だ」と割り切っている人は、読み手にも書き手にも少ないようだ。おかげで、コラムやエッセーの仕事をすると、風圧がすごい。まあ、おかげで話題になって次の仕事にもつながるのだけど(笑)。
ただ、本当に心底勘違いされてしまうと、さすがに気の毒になってしまう。それに、僕もたまには「掌田さんっていい人なんだ」って思われたいし(笑)。なにより「面 白い文章を書くためにいろいろ考えている」ことが全く理解されないのもさびしい。テクニカルライティングの世界では、どうも書いてある知識の量と正確さにばかり目が向いて、「文章表現の重要さ」が顧みられない感じがあるんだよね。それが解説書の類いならわかるけど、エッセーまでそんな感覚で読まれてしまうのはちょっと情けない。
文章は、魔法だ。文字だけで、相手を笑わせたり怒らせたり、読み手の感情を自由にあやつることができる。僕はそう信じている。文章の持つ魔力を信じている。それを信じることができずしてもの書きがつとまるものか。(←はい、例の「熱くなる」テクニックですね(笑))
僕の書くエッセーやコラムは、いわばその実験台だ。もし、どこかで僕のエッセーなどを読む機会があったら、ちょびっとだけそのことを思い出してみて下さい。――文字の向こう側で、僕があなたの感情をあやつっている姿が、きっと見えるかも…。
エッセー(98.10.12追加)
AppleScriptは、7.5よりシステムに標準で組み込まれるようになったアプリケーション制御のスクリプト言語だ。その特徴の一つに「多言語表現が可能である」ということがあげられるだろう。MacOSの日本語版では、英語の他に日本語によるスクリプティングが可能になっていた。
この「日本語によるスクリプティング」に惚れて、ぼくはここ数年、ずっと「AppleScriptは日本語で書こう!」といい続けてきた。AppleScriptの本も、初期の頃の1冊を除いて後は全て日本語で書いたし、雑誌記事なども全て日本語を使った。それもこれも、日本語によるスクリプティングを定着させるためだった。
が、AppleScriptユーザーの中には、「日本語スクリプティングはダメだ!」という人も相当数いた。いや、その方が多かったかも知れない。多くの人は単に好みの問題として英語を選んだのだろうが、中には、日本語スクリプティングを普及させないことに全力を投入しているような人もごくごく一部だがいた。彼らは今頃凱歌をあげていることだろう。「ほら見ろ! やっぱり日本語なんて普及しなかった!」と。
実に悲しいことだ。悲しいのは「日本語が普及しなかった」ことではない。理想論の戦いとして始めたつもりの「スクリプト論争」が、そんな枝葉の現実問題にすり変わってしまったことが何より情けないのだ。
スクリプト言語は日本語と英語とどちらがいいか――多くの人はそういう見方をしていた。それがくやしかった。情けなかった。そうではなかったはずだ。
「全ての国のユーザーがみんな英語でプログラムを書く世界」と「それぞれの国のユーザーが、自分の母国語でプログラムを書く世界」――AppleScriptが提起したのは、「このどちらの世界を我々は選ぶのか」という問いだった。そうじゃないか? 少なくともぼくはそうだと思った。だからこそ、日本語でスクリプトを書くことにこだわったのだ。
理想論と現実論。多くの場合、理想主義は嫌われる。「だって現実問題として…」という意見が常に勝ちをおさめる。現実問題として、今の日本語スクリプトはわかりにくい。現実問題として、今は日本語対応しているソフトが少ない。どれもごもっともな理由だ。だから日本語は英語には勝てなかった。そのぐらいのことはもちろん戦う前からわかっていたさ。
「そうやって理想論ばかりいってるから、掌田はダメなんだ」と人はいう。なにしろ、これで0勝3敗だ。HyperCard、Media Objects、日本語AppleScript。ぼくが手掛けたものはみんな負けいくさになる。いいだろう、負け数はぼくの勲章だ。
それでもぼくは理想論を支持したし、これからも支持し続ける。ぼくはWindowsの時代にMacを選んだ人間なのだ。理想が現実に勝つことを信じずして、どうしてMacを使えるだろうか。
エッセー(97.11.17追加)
どうも陳舜臣さんの「チンギスハンの一族」とかの小説が売れたことと中国史ブームとが重なってこういう結果になったらしい。チンギス汗といえば、史上稀にみる虐殺を行なった人間である。そういう人間の下で働きたい、ということの意味がよくわからない。
どうやら最近は「頑固そうだが信念を持っている人」というのが若者に支持されるらしい。頑固親父っぽい人だな、うん。そういえば寺内勘太郎一家がCMで復活したりしてるのを見ると頷けないことはない。
それを逆から見れば、つまりいかに頑固に信念を持っている人が稀少になってきたか、ということなんだろう。そして「ああ、オレはあそこまでしっかりと信念を持ちつづけることはできない、ああなんてすてきだ」とか思っちゃったりするんだろう。そもそも、その程度のことで昨年までは見向きもされなかったチンギス汗が1位になってしまうことからも、いかにみんな信念を持っていないかがわかるね(笑)。
だけど、そういう「信念を持ち続けている人に憧れる人」あるいは「頑固に信念を持ちつづける人」というのを見ていると、ふと疑問に思うことがある。それは、その信念は本当に正しいのか、ということだ。
例えば国会で大声を張り上げている政治家の皆さん。例えば街頭で騒音をまき散らしている右翼の皆さん。例えばどっかのビルを爆破しているテロリストの皆さん。いずれもすばらしく頑固に信念を持ち続けていらっしゃる。けれど、たいていは支持されない。それは、その信念が受け入れられないからだね。
時として人は錯覚してしまうことがある。信念が正しいかどうかではなく、信念を持ちつづけることが素晴らしいのだ、と。特に自分自身がその渦中にある場合、さまざまな圧力に屈せず信念を持ちつづける自分に陶酔してしまっていることに気づかない。それは実は「不当な圧力」ではなく、単に「君、間違ってるよ」と教えてくれているだけだったりするのに、そのことに気づかず信念を曲げないことが全てに優先すると思い込んでしまう。そうなったらそれはもう宗教みたいなものだ。君が頑固に守り続けているものは信念ではなく信心ではないのか?
さまざまな反対に屈せず信念を貫き通すのは、実はたやすいことなのだ。それよりも、自分の守り続けてきた信念が間違っていることに気付いた瞬間、それを投げ捨てることのほうが遥かに難しいのだ。そんなことをすれば、自分の信用は失墜する。今までついてきてくれた人は離れていく。回りから後ろ指をさされる、「あいつは転んだ」といって。嘲笑される。「風見鶏」と蔑まれる。それに耐えて、君は自分の信念を投げ捨てることができるか? きっとできまい。それが重要でより多くの人に注目されていればいるほど、曲げることなどできまい。例え間違っているとわかっていても、それまで守ってきた信念にすがって生きたほうがどんなに楽なことか。
ぼくは「信念を貫き通す人間」よりも、「間違いに気づいた瞬間、それを軽やかに捨て去ることのできる人間」に憧れる。よく調べると、チンギス汗は配下のものからの提言が正しいと思えばすぐにそれを採用する度量を持っていたという。それを聞いて、ぼくはちょっと安心している(笑)。
エッセー(97.11.13追加)
−−というのは、実はぼくが勝手に作った格言であるけれど、最近になってこの2種類の人間のことを深く深く考えるようになってしまった。
ぼくのところには毎日何通ものメールが届く。その半数は、質問のメールだ。仕事柄、ぼくはあちこちの雑誌に記事を書いていたりするので、それに対する質問や、関連する事柄に対する相談などが多い。
実は「相談」というのは、案外こちらも喜んで返事を書いてしまったりする。「プログラミングを始めたいんですけど、○○と××、どちらが使いやすいでしょうか」などとあると、うーんオレも偉くなったもんだなあ、こうして人に頼られるようになったとは、などと思いながらほいほい返事してしまったりする。つまるところ「相談」というのは「意見」を求められるわけであって、「間違っていたぞ」と後で怒られる気遣いもない。
ところが「質問」となると話は違う。下手に間違ったことを教えてしまったら「お前のせいでとんでもないことになったぞ」などというお叱りを受けかねない。特にプログラミング関係の場合、適当に答えてしまうと「おかげでシステムが破壊されました」などといったお礼状を受け取ることにもなりかねないので、いちいち細かく調べて実証してからでないと返事が書けないのだ。これはかなり大変なことだ。
ここで「オレサマに質問なんぞするな、といいたいのか?」などと早合点してもらっては困る。そういうことをいっているのではないのだ。そうした質疑応答の毎日を送っている内に、ふとこういうことを思うようになったのである。それは「質問する人の多くは永遠に質問する人のままで、答える人にはならない」ということだ。
もちろん、誰だって最初から何もかもわかるわけではない。「聞くは一時の恥、聞かざるは一生の恥」ということもある。知らないことが恥ずかしいことではないし、わからないことを聞くのが悪いことでもない。
しかし、それでは人にいろいろ聞いて成長した人間が、今度はいろんな人に答えてあげる人間になるか、というと、実は案外そうではなかったりする。質問する人の多くは、いつまでたっても質問する人のままなのだ。
こういうと、多くの人はこう思うだろう。「それじゃ、答える人は最初っから答える人だったのか? 質問する人だったことはないのか?」と。
そうなのだ。「答える人」の多くは、昔から答える人だったのである。彼らは何も知らない初心者の頃から、決して「質問する人」ではなかった。わからなければ、彼は何とかして自分で答えを見つけ、決して人に質問をしたりはしなかった。「人に頭を下げて教えを乞う」ということが死んでもできない人種だったのだ。
なぜ人に聞かないのか。それは単に「恥ずかしいから」「イヤだから」といったことだけではないように思う。彼らは、皆、人に質問することで何を失うか知っていたからだ。
人に質問する時、人は何かを失う。もし自力でなんとかして解決できたならば得られただろう何かを失っているのだ。そして人に答える時、人は何かを得ている。おそらく、本来ならば質問した人が得られただろう何か、を。そうして「答える人」は日に日に成長し、「質問する人」はいつまでたっても同じ場所に留まっている。
この世に「絶対にわからない」ことはそう多くはない。答える人の多くはそう思っている。実際、答える人は、質問する人には見えなかった多くの世界を知っている。そしてこの先、わからないことにぶつかる度に、その世界は確実に広がっていくのだ。
…さて。何か質問はありませんか?
※その昔書いたお話(97.11.6追加)
…そうですか、それじゃ話してあげましょうね。これは、ひょっとして今のあなたのためにもなる話かもしれませんし。
婆とおじい様が知り合ったきっかけは、文通だったのですよ。その頃の女学校といったら、それはもう今のあなたなどにはきっと想像もできないでしょうね。男の方と知り合うなんてことは、しょせんあなた、夢物語みたいなものですよ。
それでも、婆だって若かったですしね。なんとかして殿方のお友だちができないものか…そう考えていたときですよ、寄宿舎の友だちが巷ではやりの文芸雑誌というのを見せてくれたのは。そこで、初めて文通というのを知ったのですよ。
もちろん、当時、女でそんなものに応募するなんてはしたない子は滅多にいませんでしたから、婆の名前が載ったときには、それはもうすごいお手紙の山が届いたものです。…ま、何をまあそんな顔をして。婆にだって若い頃はあったのですよ。
婆はその中で、何人かの殿方に返事を書きました。どうか次はお写真を送ってくださいまし、とね。さっそく送り返して下さった方は二人。一人は、まあごく当り前な感じの平凡な殿方で、ぱっと心をとらえるような方ではありませんでしたけれど、もう一人はね、これがあなた、今でも思い出すだけで顔がほてってしまうほど、素敵な殿方だったのですよ。
返事ですか。…そうなのですよ、そこで婆は、はたと困ってしまったのです。それは、確かに当時は写真なんて贅沢ものでしたけれど、殿方との交際には代えられません。問題はそんなことではないのですよ。
婆はね、自分でいうのも何だけれども、あまり美しい少女ではなかったのですよ。まあ醜いというほどではなかったけれど、かといって美人でもないし、どこといって取り柄のない平凡な女だったのです。−−もちろん、次にはこちらから写真を送らなければならないでしょう? けれど、そのすてきな方に婆の本当の写真を送ったら、きっとご返事はいただけないだろう、そう思ったのです。
そこでね、婆は、もう一人のパッとしない殿方にはそのまま私の写真を送って、その素敵な殿方には、姉の写真を送ってしまったのです。…そうですよ、一昨年に亡くなった、婆のお姉さんです。あの方はね、若い頃は小町娘といわれて本当にきれいな、姿のいい方だったのですよ。
その素敵な殿方との文通は、何年も続きました。その方はお顔だけじゃなくて、心もとても優しくて、誠実な方でした。けれど、ある時に、そのおつきあいも終わりになるのでは、という出来事が起きてしまったのです。
その方がね、上京して、婆に逢いに来ると知らせてきたのですよ。
婆は、自分を偽ってきたことを心底後悔しましたよ。まさか、姉に打ち明けて逢ってもらうわけにもいきませんでしょう?
長い時間考えた末、婆はね、逢って全てを話そうと心に決めたのです。長い文通で、その方がとても誠実な方であることは、婆にもよくわかっていました。それで、心から詫びれば、きっと許してくれるだろう−−そう思ったのですよ。
…それから先のことは、そう話すことなどありませんよ。そう、婆は待ち合わせの場所に出かけていきました。そしてそこには−−
−−そこには、婆が自分の写真を送った、もう一人の平凡な文通相手の殿方が待っていらしたのです。…これが、あなたのおじい様とのなれそめですよ。
…あら、もうこんな時間だわ。あなたももう休まないと。明日、寝坊でもしたら大変ですよ。明日はあなた、そのなんとかいうパソコン通信の殿方と、初めて逢う日なのでしょう?