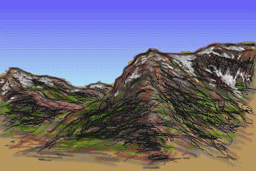
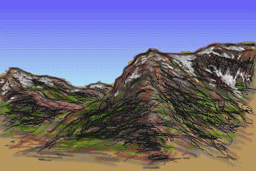
一応、ガキの頃は野球で育った年代なので、プロ野球衰退の原因を半ば真剣に考えていたのだけど、最近になって一つの結論に到達した。それは、「解説者」である。プロ野球の解説者は、選手がいかに無能で阿呆で出来損ないかを懇切丁寧に解説する。一方、Jリーグの解説者は、選手がいかに素晴しい技術を披露してくれたかをとてもわかりやすく解説してくれる。この違いは大きい。例えば。
「いやー、3番の松井、引っかけてボテボテの内野ゴロに終わりました」
その1「松井はダメですねえ。よく見れば、あれはボールですよ。しかも去年から腰の切れが悪くなってるから、ああいう外角の球は引っぱろうとしても引っぱれない。全く、3番としては情けないですねえ」
その2「いやあ、さすがに調子がいいときの今中は打てませんねえ。さっきの素晴しいストレートの後に、この蝿が止まるようなションベンカーブでしょう。これじゃあ、さすがの松井も引っかかりますよ。彼は昨年から腰の切れが悪くなってますが、それでもなんとか当てたのはさすがですね」
さて、この2つの解説を比べてほしい。前者の場合、松井君はほんとにでくの坊のように見えるけど、後者だと「そうか、相手のほうが上手だったんだなあ」と思うでしょ? 同じプレイでも、解説の仕方で良く見えたり悪く見えたりするのだ。
こういう解説ばかり聞かされると、プロ野球ファンは、いつの間にかノーガキばかり山のように覚えて、実際のプレイを見なくなってしまう。そして、翌日の朝刊のスポーツ面を見ながら「うーむ、松井はこんなことやってるからダメなんだな」などというようになる。こうなったら末期症状である。おい、おっさん、あんた新聞だけで試合内容がわかるんかね?
そう。ノーガキが多くなると、大抵のスポーツや文化は衰退するのだ。歌舞伎とか能とかも、やたらお偉いさんがノーガキばかりたれるようになったから衰退したんじゃないか。小説なんかも、「文芸評論家」とか呼ばれる牛の尻の蝿がノーガキばかりたれるもんでつまらなくなったのだ。そうだそうだそうに決まった。この辺、強引だと思うだろうが黙れ黙れ。
ノーガキだけがもてはやされるようになると文化は衰退する。反面、それにたかる蝿どもはそれに反して隆盛を誇るようになる。文学が衰退すると、その生き血を吸っている文芸評論は成長し、野球は衰退しても野球解説者はどんどん増えていく。世の中は「寄生する側」と「される側」に分かれており、どちらか一方が反映すると、もう一方は衰退していくのである。ぼくらは、「果たしてこいつは寄生虫かそうでないか」を注意深く見分けられる目を養わなければいけない。
では、ある人間や世界が「寄生虫側」かどうか確かめるにはどうしたらいいか。これは実をいうと簡単である。
1・寄生虫は、やたら難しい言葉、特に専門用語やカタカナ言葉を多用する。そうすることで、いかに自分が物知りで偉いかを印象づけるのである。
2.寄生虫は、なんでもかんでも「ダメだ」という。相手を否定することで、「おれのほうが偉いんだ」と印象づけるためである。
この2つの特徴があるものは、大体寄生虫もしくは牛の尻の蝿だと思って間違いない。
ところで、我らがパソコン界だが…いや、よそう(笑)。
ついこの間から、私はちょっとばかり変わった決まり事を作って実行に移している。それは「ラーメンに調味料を追加しない」ということ。−−それまでは、ラーメンを頼むと、何も考えることなく胡椒をバサバサと振りかけていたのだが、それをやめ、出て来たものをそのまま何も手を加えずにいただくことにしたのだ。
そうして何が変わったか。それは、ラーメンの味に対する感覚である。それまで行きつけだったラーメン屋でも、そうして何も足さずに食べるようになると「あれ?こんな味だっけ?」と思うくらいに味が違っていることが多いのだ。
そう。私はそれまで「店の味」ではなく、「オレの味」をあじわっていたに過ぎなかったのだ。胡椒をドバドバと入れ、どのラーメンも全て同じ辛さにしてしまうのだから、その店が本来「これがうちの味です!」と出していたものとは似ても似つかぬ味になっていたはず。それを私は「おいしいおいしい」とばかりに食べていたのである。
デフォルトというのは悲しい。標準で用意されているものというのは「誰もがとりあえずオッケーできる最低限のもの」というニュアンスで受け取られることが多い。デフォルトをそのまま楽しむのはドシロウトのすることで、ばきばきにカスタマイズするのがプロなのだ、といわんばかりの風潮が、今の世の中にはちょびっとだけある。
ラーメンには胡椒からラー油、七味を適度にいれ、それでも足りずに「おやっさん、オレ、バターちょっと多めにね!」などと叫ぶのがラーメン通だと思っている。サラダには間違ってもとんかつソースや醤油をかけてはならず、「なんたらかんたらドレッシングのへもほけれ風味、ある?」などと聞かないといけない。そうして、本来その料理が形作っていた味をぶちこわしておいて「最近のフランス料理はコクがイマイチでね…」などと偉そうにのたまう、それが食通の証しなのだ。
同じことはパソコンでもいえる。それどころか、パソコンこそ「カスタマイズせぬ者はパソコンユーザーにあらず」というくらいに、カスタマイズの嵐が吹きまくっている世界なのだ。デフォルトでインストールされている環境をそのまま使うなんてバカじゃないか、とマックユーザーもウインドウズユーザーもみんな思っている。
私は、自分のパソコンでは、極力デフォルトの環境に近い状態で使うようつとめている。フェップも、マックでは「ことえり」、ウインドウズでは「IME」だ。どちらも標準添付で「猿よりオバカ」といわれている日本語変換プログラムである。
デフォルト環境に慣れて一番に感じるのは、「デフォルトは美しい」ということだ。マックにしろウインドウズにしろ、デフォルトは必要最小限の機能を、もっともわかりやすくまとめたものである。そこには、開発者の理念があり、使うにつれてそれが感覚的にわかってくる。確かに機能的には弱いだろうが、しかしデフォルトには無駄がない。無駄がないものはとても美しい。
そしてデフォルトの美しさに慣れたところで辺りを見回してみるに、いかにも「パワーユーザーです!」といわんばかりにカスタマイズし尽くしているマシンのなんと醜悪なことか。色使いはケバケバしく、あちこちに無意味なくらいにメニューやアイコンやその他わけのわからないものが並び、ユーザーは喜々としてマウスとキーボードを複雑怪奇に操作している。そして誇らしげに「いやあ、マックってもんはねえ…」などとのたまうのである。いかにも「オレは全てを知っているぞ」といわんばかりに。
君が知っているのは、マックの環境ではなく、「君」の環境なのだ。そのことを、誰か教えてやってくれないか?
その店の名前を仮に「R」としておく。中野駅から歩いて5分ほどのこじんまりとした店だ。卵料理が自慢というので、とある日の夜、ぼくは知人たちと連れ立ってその店を訪れたのだ。
入った直後、ぼくは即座に「しまった」と思った。その店は、いかにもかわいいっぽいランプやテーブルが並べられており、いかにものーてんきなカップルがいかにもロマンチックな雰囲気を楽しみにやってくるところだ、と気が付いたからだ。とても三十ヅラした男が連れ立って入るようなところではない。
がしかし、入り口をくぐってしまったのに引き返すのも気が引ける。ぼくらは腹をくくり、かわいいテーブルについて自慢の卵料理を注文したのである。
そして出てきた料理というのが−−なんと表現すればいいのだろうか。とにかく「まずい」のである。それもごく当り前のまずさとは違う、なんともいえないまずさなのだ。
普通「まずい」というのは、手を抜いているか、材料が悪いか、ともかく客のことなんか考えず適当に作ったもの、という感じが強い。ところがこの店は違うのだ。材料も非常によいものを使っており、料理もていねいに味付けし調理されており、おそらく料理人の腕もかなりのものなのだろう。そうして実にきめ細かな神経で作られた料理であることは食べてすぐにわかるのだ。
ところが、彼等の「味」が全く間違っているのである。彼等は、とんでもない味を「もっともおいしい味」と勘違いして、一生懸命その味に近づこうと努力している、という感じなのであった。
まあ、味覚なんてものは人によって違うのだし、ぼくだって別にグルメというほどの人間ではない。松屋の牛丼でさえ「うまいうまい」と喜んで食べるような人間だ。しかし、とりあえず普通の日本人が普通にうまいと思うものぐらいはわかるつもりである。
ところが−−。実に不思議なことに、その店で食事するカップル(ぼくら以外は全てカップルだったのだ)は、みんな実においしそうに料理を楽しんでいるではないか! そして、どうやらその店は、特に若いカップルの間でとても人気があるようで、次から次へと客が訪れるのであった。
これは一体どうしたことだ? なぜ、こんなにこの店は流行っているのか? しかも、みんなうまそうに食べているのか?
この謎を解明できる理由は2つしかない。一つは「ぼくらと彼等は全く違う味覚をしているのだ」ということ、もう一つは「彼等は味わっていないのだ」ということだ。
そう。実際、彼等は味わっていないのだ。それは自分でも経験がある。若い頃、女の子をデートに誘って連れていく店をどうやって選んだか。雰囲気がよくて、ロマンチックで、そして有名で、「あ、この店有名なのよね」と女の子にいわれてちょっと得意げに「ああ、そうみたいね」なんて答えちゃったりするような、そういう店である。そこで何を食ったか、どんな味だったかなんて覚えちゃいない。女の子と一緒にメシを食うのだ、豚の餌だろうが馬の餌だろうがうまいに決まっている。
その「R」という店は、次から次へとカップルがやってきて繁盛するので、「そうか、これがおいしいのだ!」と勘違いし、一生懸命まずい味を作る努力をしてしまったのだろう。そうだそうだ、そうに決まった。
こういう「全く見当違いの努力」というのは実に困る。不真面目なら文句の付けようもあるが、彼等は本当に「それが正しい」と信じて日夜努力しているのだ。彼等は一人一人は本当に真面目で勤勉な人達なのだろう。きっとその努力は賞賛するに値するものなのだ。方向さえ間違えなければ。
この世には、こうした見当違いの方向へ進歩してしまったものがたくさんある。そして、それを信じて日夜がんばる人達をみると、ぼくは何といえばいいのか言葉につまるのだ。その気持ち、君だってわかるだろう?
……というような話を君にしたかったのだよ、ウインドウズユーザーのK君。
病院というと、ぼくは怖いイメージしかなかったのだけど、最近は「わかりやすい医療」というのを心がけているようで、先生も気さくでわかりやすい感じの人でほっとした。なんでも、専門用語などをずらずら並べて「治療は医者に任せておけばいいんだ」といわんばかりの態度ってのは今は流行らないようで、最近はとにかく病名や治療方法などをわかりやすく説明するようになってるんだそうだ。
ぼくの病名は良性突発性めまい症とかいうんだそうで、三十過ぎた人のよさそうな先生は、一生懸命それをぼくに説明してくれた。
「…いいですか、『良性』は、悪性のものではない、ということですね。『突発性』は、突然起こる、ということですね。『めまい症』は、めまいが起きる病気、ですね。ですから『良性突発性めまい症』というのは、良性の、突発性の、めまい症、と、そういうわけなんですね。わかりますね?」
その説明を聞いて、ぼくは吹き出しそうになったのだけど、先生の失礼にならないようぐっと我慢し、廊下に出てからげらげら笑い転げたのであった。
物事をやさしく説明する、と口で言うのは簡単だ。「もっとわかりやすくしよう!」というのは、基本的にはとてもよいことだと思う。特に、医療にしろコンピュータにしろ、専門用語が湾岸戦争のイラクのように飛び交っている世界では、普通のわかりやすい言葉でものごとを説明するのは大切だ。
だがしかし、多くのところで「やさしい」ということを取り違えて、相手を阿呆だと思ってるんじゃないか、てな説明をしていることが結構多い。特に、パソコンの世界ではそういうことが異様に多い気がする。
例えば。あなたは、ウインドウズ95のパッケージに書かれている説明をじっくりと読んだことがあるだろうか。そこには、95の宣伝文句としてこんなことが書いてある。
「●もっとかんたんに、そして速く!
・…プリンタやモデム、サウンドカードなど周辺機器の増設は、プラグアンドプレイにより必要な設定は自動的に行なわれます」
ほうほうなるほど、しかしプラグアンドプレイってのは何だろう?と思って回りをよく見ると、傍らにはちゃんとその説明がしてある。
「プラグアンドプレイ
プラグアンドプレイテクノロジーがハードウェアの設定を自動化します」
…これをわかりやすい説明文だと思って書いた奴の顔が見てみたい。さっきの「良性突発性めまい症というのは、良性の突発性のめまい症です」というのとおんなじじゃないか、おいっ。
専門用語の世界に慣れ切っている人間というのは、それらのわからない人間を「バカ」だと思っている。そう考えて間違いない。特に、その世界でものすごく優秀な奴ほど、回りをものすごくバカだと考えている。そして哀しいことに、そういう人間ほど「そう思っているお前が実は一番バカなのだ」ということに気がつかないのだ。
「…ね、インターネットってどういうものなの?」
「まあ、あれはネットワークのネットワークだな、うん」
「それじゃわかんないわよ。もっとやさしく教えてよ」
「じゃ、ネットワークってのはわかるだろう?」
「うん…」
「だから、インターネットってのは、ネットワークを、ネットワークしたものなんだよ。わかるだろ?」
…こういうバカ、あなたの回りにもいない?
「すいません、えーと、これ(かりかりまんを指差す)って、どういうもんです?」
「ハイッ、えっとですね、カレーパンの中味を肉マンの具にしたような感じのものです」
「へえ。−−じゃあ、カレー味ってのは?」
「えっと、カレーパンの…」
「…中味をカレーにしたやつ?」
「−−−−」
結局、よくわからんので一通り買って食べたところ、カレー味はやっぱりカレーパンとほとんど区別がつかなかった。ま、確かに「カレーのつまったカレーパン」で間違ってはいなかったけど(笑)。
ぼくらは、物事を相手に説明するときに、「比喩」とか「たとえ」というのをよく使う。わかりにくいイメージを、誰もが知っていることに置き換えることで、うまく相手に説明することができると思っている。けれど、実をいえば多くの場合、「比喩」はかえって話を混乱させるだけだったりするのだ。
比喩というのは難しい。たとえば、パソコンの世界でも、この「比喩」というやつはやたらと登場する。
「はい、みなさーん。このパソコンの画面のことをデスクトップといいます。つまり、皆さんが普段使っている机の上がそのままパソコンの中に表示されているようになってるんですね」
しかし、机の上にゴミ箱を置いている人間が一体どれだけいるというのだろうか。
「ハードディスクはいってみれば倉庫みたいなものです。ここにいろんな書類やソフトを保管しておけるんですね」
しかし、倉庫は突然中身が消えてしまったりはしない。「ハードディスクがとんだ」というのを彼女はどう説明するのか。「火事になった」とでもいうつもりかね?
多くの「作る側」「説明する側」の人間たちは大切なことを忘れている。伝えたいことをきちんと相手に説明できたなら、「比喩」はいらないのだ。うまく伝えることができないからこそ、第二の手段として仕方なく「たとえ話」を使うんじゃないか。
いわば、「比喩」を使うというのは、説明する側の失敗なのだ。「私はどうしてもうまく説明することができませんでした。仕方がないので、似たようなたとえを使って説明させていただきます」−−比喩を使うというのは、そういうことであるはずだ。
「…つまり、パソコンの画面は机の上と同じなんですね。はい、質問はありますか?」
「−−先生。じゃ、ゼットライトとかもついてるんですか?」
「はい、他に質問は? では次へ進みましょう…」
たとえは、「そのもの」ではなくあくまで「たとえ」でしかない。だから、何から何まで同じにはならない。デスクトップが机の上だといっても、やっぱりゼットライトは置いてないのだ。
悪いのは質問したおじさんではなく、ゼットライトから灰皿から恋人の写真の入った写真立てからクマの小さな置物まで忠実に再現できず、中途半端な「比喩」しか作り出せなかった側なのだ−−そう思うのは間違いなのだろうか?
自分たちが生み出した「比喩」は哀しいくらいに中途半端な代物なのだ−−そのことを作る側や説明する側は気づかない。かくてパソコン界にはますますわけのわからない「比喩」が生み出され、ぼくらはますますわけがわからなくなっていくのだ。
先日、ちょっと買い物があって、量販店の立ち並ぶあたりをぶらぶらしたのだけど、その安売り競争たるや信じ難いものがある。「PHS特価九八○円」というのを見たときはさすがに我が目を疑ったね。それどころか、先日テレビを見ていたところ、なんと「タダで配ってた」なんて店まであったという。一体どーなってんだ、この騒ぎは?
PHSは、いってみれば「水道の蛇口」だ。とにかく一つでも多くの蛇口を取り付ける。そのためには採算割れしようがかまわない。あとで水道代としてちゃんと回収できるのだからね。なにしろ、PHS本体は一度金を払うだけだが、その電話代は永久に払い続けなければいけないのだ。それを考えれば、タダで配っても十分儲かるわけだろう。
このPHSについて、先日不思議な調査結果というのを目にした。それは高校生を対象としたものなんだけど、それによると次のような調査結果が出たというのだ。
「ポケベルや携帯電話をもっている高校生は流行に過敏で、過食症や拒食症の経験のある人が多い。過激なダイエットに走りがちで、回りのみんなと同じだと安心する、というタイプが多い」
うーん、そういわれてみれば携帯もってる女子高生は確かにデブが多いな、とか思ったんだけど、まあそれは脇においといて、「なるほど」と思ったのは「みんなと同じだと安心する」というくだり。そういわれてみれば、なるほど思い当たるフシがないかい?
とにかく、回りと連絡がとれないと不安でしょうがない−−そういう人は確かに存在する。
例えば、友だち同士で待ち合わせをしたとしよう。そして、その中の一人が時間になっていても来なかったとする。そして不幸なことに、そいつは携帯電話をもっているのだ。
こんなとき、ここぞとばかりに登場してくるのが携帯男である。「あ、ちょっと遅れてるねぇ。電話してみる?」そういうと、得意げに相手を呼びだす。
「−−あ、うん、オレ。今どこ? あ、そう。それじゃあと15分ぐらいかな。なるほどね。そうそう、みんなもういるよ。はっはっは、何いってんだよ。そう、じゃ待ってるから。うん、じゃあまたね」そしてわれわれに「今、渋谷を過ぎたあたりだっていうから、あと15分ぐらいだよ」−−なるほど、まあ便利ではある。確かにそういうときは君の出番だ。
だが不思議なのは、それなら15分待っていればいいのに、彼は絶対にそうしないことである。自分で「15分だ」といっておきながら、彼は絶対に5分もするとまた電話する。「あ、オレオレ。今どこ? うん、山手線? あ、そう。じゃ、あと10分だな。わかったわかった」そしてわれわれに「あと10分ぐらいだってさ」−−どんなバカだって15−5=10分であるぐらい、わざわざ電話しなくったってわかる。
そして更に5分後、みんなの白い視線など全く感じないのか、彼はまたもや電話する。「あ、どう? うん、新宿は過ぎた? あ、それじゃあと5分もあれば着くね。うんうん、わかった。それじゃね」そして、「あと5分で着くよ」−−もうこのときになると誰も彼の話なんぞ聞いてはいない。
それに気づいているのかいないのか、彼はさも感に耐えぬようにこういうのだ。「いや〜、ほんっっとこういうとき、携帯って便利だよねぇ」
絶えずコミュニケーションをとってないと安心できない人−−そういう人間にとって、確かに携帯電話はとてもすばらしいものであるに違いない。彼は喜々として毎日毎晩、回り中に電話をかけまくる。そうして友だちを失っていくのである。